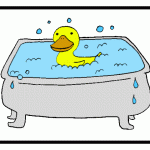2015年 12月 20日 日曜日
こんにちは!
初投稿となりますナースチームのナッピーです。
今年は暖冬だと聞いていた気がしますが、すごく寒くなってきましたね。
やっぱり冬は冬ですね!!
わたくしナッピーは年々風邪も引きやすくなり、治り難くなったと感じる今日この頃・・・。
体調管理は気をつけていきたいです。
今回はナッピーが悩み!実践している!!
「足の浮腫み」と「対策」について話したいと思います。
【足の浮腫みとは】

血液中の水分が血管やリンパ管の外に染み出し、足(脚)などの皮膚の下に溜まった状態のことを言います
入社前は病院やクリニックで普通にナースのお仕事をしていました。
今までは立ち仕事メイン!!
カルテの記録を書く時以外に座ることはほとんど無く、立ちっぱなしかバタバタと走り回っていました・・・。
そのため、勤務終了時の足の浮腫みは切実な悩みでした。
そんな生活から一変して
今はオフィスワークなので勤務中はほとんど座っています。
体力的には楽なのですが、座っているだけでもこんなに足は浮腫むのか・・・と身を持って実感しています。
立ちっぱなしも座りっぱなしもどちらも辛いですね・・・。
というわけで、「足の浮腫み」には常々悩まされており、浮腫みの改善は永遠のテーマになりそうです!!
■浮腫みの原因と対策~オフィスワーク~
冷え:冬はもちろん夏でも冷えは大敵です。ビルの空調は足元の温度調節が上手くいかないのか、夏も冬も足元の冷えが気になります。
<対策>ひざ掛けは必須アイテムですが、それだけでは寒いので、ひざ掛けにカイロを貼りつけ、レッグウォーマーを着用する!というのが最近の必需品です。
<効果>カイロは低温やけどをする可能性もあるので注意が必要ですが、レッグウォーマーは足元の冷えをかなり回避できます。わたくしナッピーが愛用しているのは、内側がシルク素材の物で蒸れがなく、温くてオススメです。その他にもボア素材やダウン素材の物もあるようです。

血行不良:運動不足で筋力低下、長時間同一体位、もちろん冷えなども原因です。
<対策>足首を回したり、足の指のグーパー運動をしたりとネットでもオフィスのデスクで出来る運動がたくさん紹介されているので実施しています。また最近は麺棒を足の裏で転がして、ツボを刺激したりしています。痛気持ちいいですよ。
足裏面棒は気をつけないと落ち着きがないと勘違いされる可能性もあるので、注意しながら実践する必要があります(笑)
他にも運動不足解消のために帰宅時は30分程度(2駅分)の歩行。(残業がほぼないのでこんなことも出来ちゃいます!)
あとはトイレに立った時にストレッチ運動やこまめにリンパを流すようにマッサージをしています。
<効果>
紹介した中で一番効果が実感されたのは「麺棒を使ったツボ刺激」と「こまめなリンパマッサージ」です。ストレッチは気分転換にもなるのでオススメです!!!
今回はわたくしナッピーの偏った見解も含めて紹介させて頂きました。
この他にも浮腫みの原因は様々なので(もしかしたら病気が原因の場合もあるようです。)放置せずに原因を見極めて対処法を実践する!必要があれば受診するなど体調管理には気をつけましょう!!
Posted by nurse005.
カテゴリー: 未分類

![lgi01a201310110700[1]](https://kangoshi-blog.net/wp-content/uploads/2015/11/lgi01a2013101107001-150x150.jpg)
![gi01a201503101600[1]](https://kangoshi-blog.net/wp-content/uploads/2015/11/gi01a20150310160012-150x150.jpg)
![item-0071[1]](https://kangoshi-blog.net/wp-content/uploads/2015/11/item-00711-150x150.png)